エピローグ:行政書士としての誇りと未来への希望
- 山崎行政書士事務所
- 1月6日
- 読了時間: 2分

夜の帳が静かに降りる頃、田中颯太は事務所の窓辺に佇んでいた。外の景色は、いくつもの依頼者の人生を支えた日々を映すかのように、控えめな輝きを放っていた。街灯の光が細い雨に滲み、オレンジ色の軌跡を描く。
机の上には、これまでの記録が山積みになっている。相続手続きに苦しむ高齢者を支えた日々、外国人労働者の不安を少しでも軽くしようと奔走した時間、そして災害に見舞われた地域住民の再生を後押しした瞬間。それぞれの書類には、無数の言葉が詰まっている。それらは単なる業務の記録ではなく、人々の生活と命の重みを支えた軌跡であり、颯太自身の成長の証だった。
ふと、耳に残る声が蘇る。
「先生がいてくれて本当に良かった。」
それは、感謝の言葉であると同時に、彼の職業に対する最大の賛辞だった。行政書士としての使命感が、その言葉によってさらに強固なものとなる。
しかし、満足感に浸る間もなく、彼の心には次なる問いが浮かぶ。
「未来の行政書士とは何か?」
答えは簡単ではない。テクノロジーが進化し、人間の感情や倫理がますます試される時代。行政書士としての役割も変容を迫られている。だが、それこそが彼にとって新たな挑戦だった。
彼は視線を遠くに向ける。夜空の向こうに広がる未来。その先に、まだ見ぬ依頼者たちの生活と希望が待っていることを知っている。
「やれるだけのことをやろう。」
独り言のように呟き、机に戻った颯太は、次の案件の準備を始める。ペンを手に取り、書類の隅に小さなメモを書き込む。その動作は、彼自身の決意の現れであり、これからの未来を切り開く第一歩だった。
窓の外の雨は、いつしか上がっていた。空には淡い星が輝き、静かな希望を秘めていた。颯太はその光に向かって微かに笑みを浮かべた。
行政書士としての誇りと未来への希望。それは彼の中で確かな形を持ち始めていた。


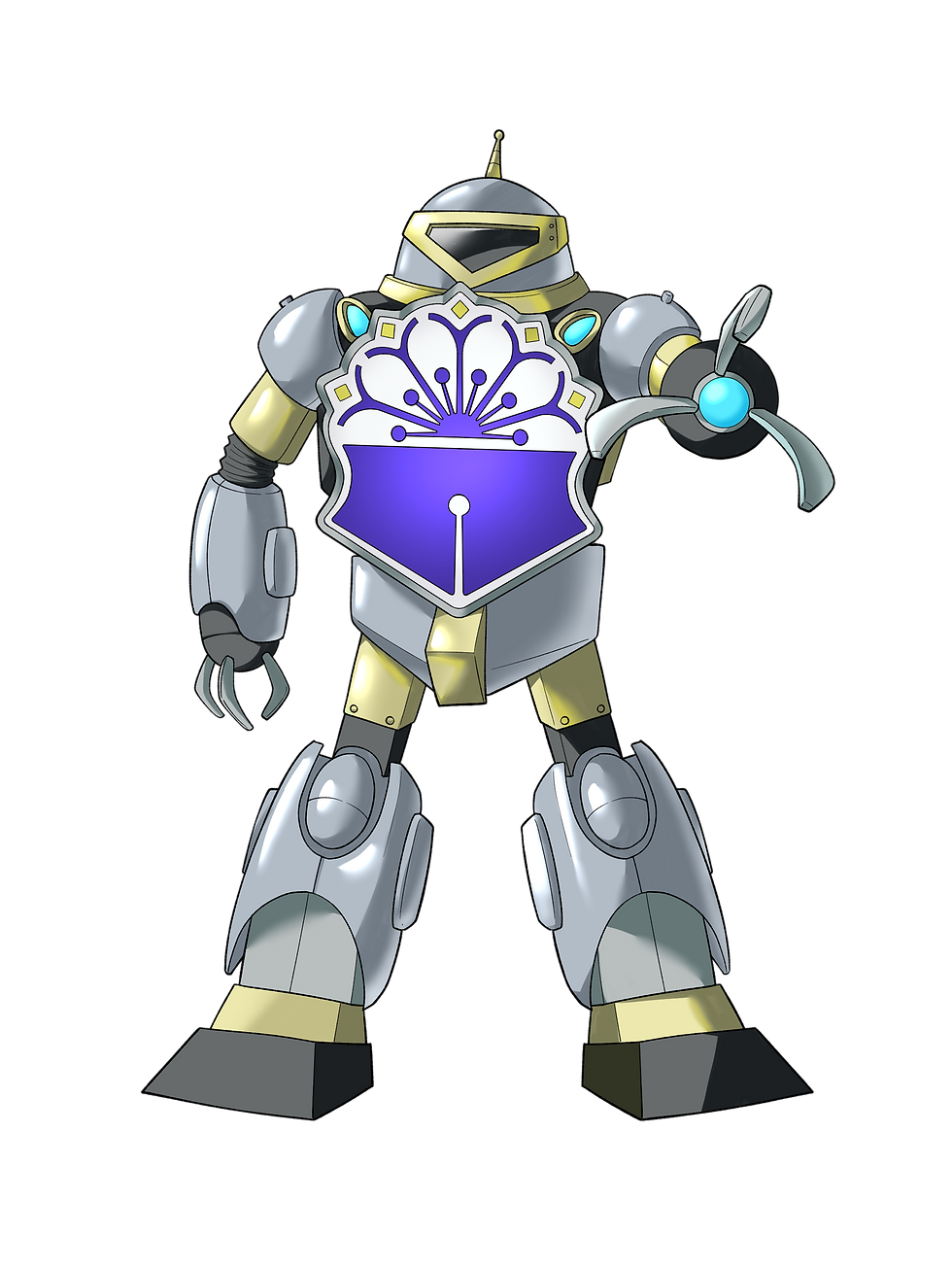


コメント