封を結ぶもの — 行政書士と皇政への憧憬
- 山崎行政書士事務所
- 1月15日
- 読了時間: 6分

1. 書類と御璽(ぎょじ)のあわい
若き行政書士・高槻(たかつき)は、一見すると物腰(ものごし)柔らかで、どこにでもいる書類屋(しょるいや)に見える。会社設立や相続手続き、許可申請などをきめ細やかにこなし、役所(やくしょ)からも「仕事が早くて正確」と定評(ていひょう)があった。だが彼の胸中(きょうちゅう)には、誰にも語らない奇妙(きみょう)な熱情(ねつじょう)が潜(ひそ)んでいる。幼いころ、ふと目にした皇居(こうきょ)の祭礼――そこに漂(ただよ)う厳粛(げんしゅく)で神秘的な空気を吸ったときから、天皇という存在に“宗教的”といえるほどの崇拝(すうはい)を抱(いだ)いていたのだ。
「現代の社会で、陛下(へいか)の印(しるし)は書面の端(はし)に押(お)される“ハンコ”ほどの意味しかないのか? ならば、俺は行政書士として書類を通し、この国の“御璽(ぎょじ)”に匹敵(ひってき)する究極の印を模(も)してみせる……」
2. 特殊な依頼、皇室ゆかりの儀式
ある日、高槻の事務所に奇妙な依頼人(いらいにん)が現れる。**山科(やましな)**と名乗るその人物は、旧華族(きゅうかぞく)に近い家系で、先祖が皇室(こうしつ)に仕えていたという。「わが家(や)の祭礼を正統(せいとう)に行いたい。だが官公庁(かんこうちょう)への許認可(きょにんか)が複雑(ふくざつ)で困(こま)っている。あなたが書類を作り、当局との交渉をまとめてほしい」と言う。だが彼の言葉にはさらに続きがあった。「この儀式は昔から“皇室の承認(しょうにん)”を得ていたとか。今も本物の御璽を――少なくともそれに近い形でいただく方法はないか?」あまりに非常識(ひじょうしき)とも思える話だが、高槻は彼の目に宿(やど)る異様(いよう)な光を見て、自分の内なる“皇室崇拝(すうはい)”と響(ひび)き合うのを感じ、あえて受けることに決める。
3. 役所の形式主義(けいしきしゅぎ)と血の匂(にお)い
高槻は役所を訪れ、申請書類を整える。だが担当者(たんとうしゃ)は「この儀式は法律上の位置づけがあいまいだ」「さらに動物(どうぶつ)や火器(かき)などの使用があるなら安全性の書類が必要」などと、細かい規定を次々と指摘(してき)してくる。捺印(なついん)のミス、印鑑証明の期限切れ、改めての書類補正(ほせい)……。膨大(ぼうだい)な事務作業に追われるうち、山科は苛立(いらだ)って「これは先祖代々(せんぞだいだい)の皇室儀式なんだ!」と声を荒(あ)らげるが、役所は冷淡(れいたん)に書類不備(ふび)を突(つ)くだけ。
しかし、高槻はそんな形式主義を“面倒くさい”と感じながらも、どこかで**「日本はこうした印鑑(いんかん)文化や書類社会を通じて国を回している……この細密(さいみつ)さが、かつての御璽(ぎょじ)や朱(しゅ)の儀式に通じるのでは」と思い始める。まるで朱肉の赤**が血を連想させ、背筋(せすじ)がゾクゾクするような感覚だ。
4. 血をもって朱印を押す?――高まる狂信(きょうしん)
書類を作りながら高槻は、そのうち「本物の御璽」として自分の血を使った朱印(しゅいん)を押すという思いつきが頭に浮かぶようになる。「死や血を賭(か)してでも天皇を支えたい……現代に生きる俺ができることは、“法”と“血”を組み合わせた究極の印鑑だ!」SNSや世間では誰もそんなこと理解しないが、彼は自分の中の衝動(しょうどう)を抑(おさ)えきれず、夜な夜な書類の端(はし)に自分の血を垂(た)らして印章(いんしょう)を押すイメージを想像して恍惚(こうこつ)とする。
5. 最後の交渉、そして破綻(はたん)
ついに儀式の申請(しんせい)も大詰(おおづめ)。山科家の強い要望で、どうにか官公庁も“条件付き許可”の線で妥協(だきょう)しそうになるが、書類上の最終印鑑(いんかん)を押す段階で、思わぬトラブルが発生(はっせい)。政治的圧力(あつりょく)が入り、上層部が「そんな怪しい儀式には許可を与えられない」とストップをかける。高槻は懸命(けんめい)に説得(せっとく)しようとするが、もはや法的根拠(こんきょ)がなく、開き直(なお)った役所や政治家に阻(はば)まれて、すべての努力(どりょく)が水泡(すいほう)に帰そうになる。
6. 闇夜の書庫、血に染(そ)まる書類
絶望(ぜつぼう)し、夜の自分の事務所の書庫(しょこ)にこもった高槻は、山積(やまづみ)の申請書や古い法令集(ほうれいしゅう)を開き、ここから逆転(ぎゃくてん)する方法はないかと思案(しあん)。しかし現実には何も手段(しゅだん)がなく、彼はついに“自分の血を朱肉がわりに使って、最終の印を押そう”と決意(けつい)する。震(ふる)える手で短刀(たんとう)を握(にぎ)り、自分の指先(ゆびさき)を切(き)って血を出し、その血を朱(あか)として書類の末尾に**“押印”**する――切腹にも似た儀式(ぎしき)だが、ここでは指先の血だけ。だが、その行為(こうい)で書類が公的に効力(こうりょく)を得られるはずもない。彼自身も分かっているのに、止(と)まらぬ狂信(きょうしん)に駆(か)られ「これが真の御璽(ぎょじ)だ……」と恍惚(こうこつ)とする。
7. 苦悶(くもん)の叫び、最期の選択
山科家に持っていくべき最後の書類を血で汚(よご)し、歯を食いしばる高槻。「これを渡(わた)せば、俺は役目を果たす。だが現代社会は決してこれを認めない……」連日の徹夜(てつや)や精神的疲労(ひろう)で追いつめられた彼は、さらに短刀を深く自分の腹へ……。「法と血が融合(ゆうごう)すれば、きっとこの国を動かせるはずなのに……現実は俺を拒(こば)むか……」涙(なみだ)を流しつつ、彼は自分の身体(からだ)を切り裂(きりさ)こうとする。切腹(せっぷく)でしか理想を証明できないと信じ込んでいるかのようだ。
8. 山科家の制止(せいし)も空しく、血まみれの床
そこへ突然(とつぜん)駆けつけた**山科伯耆(はくい)**や家人たちが、彼の自宅事務所をこじ開(あ)け、「高槻、やめろ!」と叫(さけ)びながら止めに入り、刀を取り上(あ)げようとする。だが、あまりに一瞬の出来事(できごと)。高槻は刀の刃先(はさき)を自分の腹に突(つ)き立て、血が噴(ふ)き出すように床へ散(ち)る。書類が血に染(そ)まっていく。「これが……俺の朱印(しゅいん)だ……」彼は苦しい息(いき)をしながら呟(つぶや)き、伯耆が必死(ひっし)に止血(しけつ)しようとしても間に合わない。最後の力を振り絞(しぼ)るように、床に倒(たお)れ伏(ふ)して絶命(ぜつめい)する。
9. 悲劇の後、法も血も虚(むな)しきもの
翌日、警察が来て事件性(じけんせい)が薄い自殺(じさつ)と判断(はんだん)、メディアは短く「青年行政書士の不可解(ふかかい)な自死」と報じる程度。山科家は「彼が最後まで書類を貫(つらぬ)いてくれた」と嘆(なげ)きつつも、結局は土地の問題が根本的解決(こんぽんてきかいけつ)には至(いた)らない。役所も「書類不備のまま、本人が死んだのだから……」と冷淡(れいたん)に処理し、血の朱印(しゅいん)はもちろん公的に認められない。高槻が夢見た「法と血の融合(ゆうごう)」「御璽(ぎょじ)に匹敵(ひってき)する印鑑(いんかん)」は、闇(やみ)に消え、誰の記憶にもほとんど残らない。“死の美学”は、ただ冷ややかな現実に呑(の)まれ、虚無(きょむ)だけがあとに残る。
終幕:封を結ぶもの、誰もいない
こうして**「封を結ぶもの — 行政書士と皇政への憧憬」**は幕を下(お)ろす。主人公・高槻は、法的手続き(てつづき)の実務と武士道的(ぶしどうてき)死生観(しせいかん)をどうしても統合(とうごう)しようとし、最終的に狂気(きょうき)じみた“血の朱印”へ走った末(すえ)の自害(じがい)。悲壮(ひそう)でありながら、彼の死は現代社会では単なる異常行動として扱われるだけ。書類に押される印鑑(いんかん)と、天皇の御璽(ぎょじ)を重ね合わせた彼の妄執(もうしゅう)は、現代国家の合理主義(ごうりしゅぎ)に浸食(しんしょく)され、もはや何の力にもならなかった。あえない結末に、山科家や一部の人々が悲しみに暮れるが、時間とともにすべては忘れられていく。これこそが“美と死”が現実社会に衝突(しょうとつ)した末(すえ)の儚(はかな)い崩壊(ほうかい)なのだ。


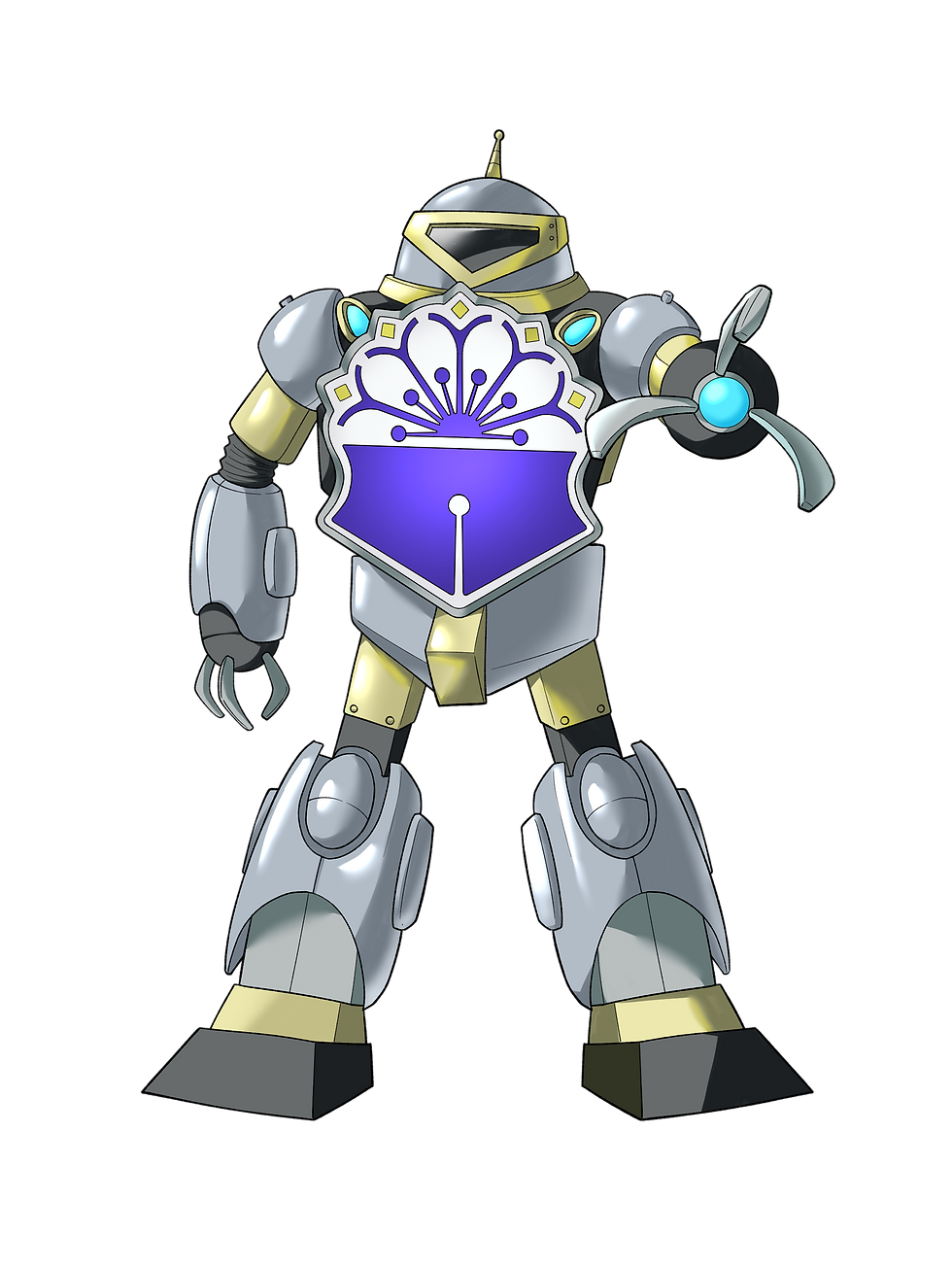


コメント