行政書士とハラスメント闇
- 山崎行政書士事務所
- 1月6日
- 読了時間: 22分

序章
雨上がりのアスファルトに街灯の残照が滲む東京下町。昭和の風情を色濃く残す一角に、「小山行政法務事務所」という小さな表札が掲げられている。周囲に比べると古めかしい木造のビルの二階、階段をぎしぎしと踏みしめて上がると、黒いスーツを着た男がデスクに向かって書類を睨んでいた。
男の名は小山茂樹(こやま しげき)。四十代半ばに差しかかり、人生の節目をいくつか経験してきた顔つきだ。かつては大手企業の法務部で契約関連の実務に携わっていたが、ある日突如として会社を辞め、行政書士としての道を選んだ。穏やかな物腰と確かな知識から、地元の中小企業や個人事業主からの信頼は厚い。彼の元には、相続関係や許認可に関するありふれた相談のほか、最近増え始めた“ハラスメント”問題への助言依頼も増えている。
小山は先ほどから、企業の就業規則に関する依頼書に目を走らせていた。依頼元は関東近郊に事業所を構える「東邦産業株式会社」。パワハラやセクハラ等、社内ハラスメントを予防する規程類の整備をして欲しいという。最近、労働関係法令の改正が進み、企業はハラスメント防止措置の強化を迫られている。行政書士として関与できる領域は文書作成や規程整備に留まるものの、「人間関係の闇」を垣間見る機会も多い。
やや古びた蛍光灯の下で書面を読み進める小山の脳裏には、この依頼が今後どういった波紋を呼ぶのか、得体の知れない不安がかすかに忍んでいた。パワハラやセクハラの影は、往々にして企業の深部に根を下ろし、あらゆる人間の意図や思惑が入り乱れた上に展開される。何か大きな事件に巻き込まれはしないか……そんな予感が、デスクの隅に置かれた手帳のように消えずに存在していた。
第一章 最初の相談者
翌朝、小山が事務所を開いて間もなく、ドアベルが微かな音を立てた。入ってきたのは二十代後半と思しき女性。スーツ姿に身を包みながらも、その目にはかすかな疲れが漂っている。名刺を差し出した彼女の名は前原可奈子(まえはら かなこ)。都内にある医療機器メーカーに勤めているらしい。
「突然お時間をいただいてすみません。ウェブで調べて、小山先生に相談できることを知りました」
柔らかな声音とは裏腹に、声の奥には何か張り詰めたものがある。彼女はバッグから書類の束を取り出すと、少し震える手つきで小山に差し出した。そこには、上司からの厳しい指導の記録とも取れるメモやメールのコピーがぎっしりと貼り付けられていた。
「上司が私だけを会議中に吊るし上げるんです。営業成績が悪いわけでもないのに、まるで私を見せしめにするかのように……。何を言っても『お前は無能だ』とか、『こんな簡単な仕事もできないのか』と罵られます。他の同僚も見て見ぬふりをしていて、毎日、会社へ行くのが辛いんです」
小山は、書類をめくりながら彼女の話に耳を澄ます。典型的なパワハラの手口のように思えたが、そこには個人と組織の闇が複雑に入り組んでいる可能性がある。上司はなぜ彼女をそこまで執拗に責め立てるのか。背景には会社内部の利権争い、あるいは業績不振が関係しているのかもしれない。
「私も弁護士に相談するべきか迷ったんです。ただ、訴訟にまで踏み込むのは抵抗があって……。まずは証拠を確保して、会社に改善を求める文書を送りたい。小山先生は、そういう書類作成のサポートができると拝見しました」
前原の瞳には期待と不安が入り混じる。そこで小山は静かに頷き、可能な範囲を説明した。行政書士は、内容証明郵便や告知文書、示談書などの文書作成を業として行うことができる。また、会社の就業規則や社内規程の整備にも携われる。しかし法的見解を示す“法律相談”の範疇に踏み込みすぎると、弁護士法違反となりかねない。小山はそのことを丁寧に伝え、前原は「それでもいいからお願いしたい」と返した。
「わかりました。まずは状況の整理から始めましょう。これはあくまで書類作成を通じて、会社に改善を促すというスタンスです。もし、その後に法的なトラブルへ発展しそうなら、信頼できる弁護士を紹介します」
そう言い終えたとき、前原の顔から力が抜けたように見えた。彼女にとっては“何か手を打てるかもしれない”という事実だけでも、救いになったのだろう。
第二章 闇の片鱗
数日後、小山は前原の資料を基に、会社宛てに送る文書の草案を練っていた。内容証明郵便で送ることによる心理的効果は大きい。会社としては「正式に記録が残る文書」と受け取るため、放置はしづらいはず。だが、小山には一抹の不安があった。こうした文書を送ることで、かえって社内で前原が孤立する危険性もある。
やがてパソコンの画面に浮かぶ一通の文案。「パワハラの具体的な事例と、それによる被害」「会社に求めるハラスメント改善策の提示」を軸にまとめたものだ。これに前原が納得し、証拠の裏付けがきちんとあることを確認した上で、送付へと進める——。
しかし、その矢先だった。事務所の電話が鳴り、小山が受話器を取ると、低い男の声が聞こえてきた。
「……あんた、うちの会社にケチをつけるつもりか?」
暗い底から聞こえるような声に、小山の背筋が凍った。声の主は名乗ろうとしなかったが、前原が勤務する会社関係者であることは間違いないだろう。小山はあくまで冷静を装い、用件を訊ねる。
「申し訳ありませんが、どなた様でしょうか。お話を伺うには、正式に面会のアポイントを——」
しかし返事は途切れ、無言が続く。小山が痺れを切らして再び呼びかけたときには、もう電話は切れていた。受話器を戻した後も、重い不気味さが事務所を覆っている。これは前兆に過ぎないのか、それともすでに圧力が始まっているのか。小山はため息をつき、一旦電話の件をメモに残しておいた。
第三章 東邦産業からの依頼
一方、小山が以前より進めていた別の案件では、企業規模の大きい「東邦産業株式会社」が社内のハラスメント防止を定める就業規則やガイドラインの整備を依頼してきていた。大手とまではいかないが、関東圏内でそこそこのシェアを持つ製造業の老舗だという。
担当者として現れたのは総務部係長の近藤淳司(こんどう あつし)。四十代前半、メガネ越しの鋭い目つきが印象的で、会社の事情をよく知る人物らしく見えた。打合せの場で、近藤は早口ながら要点をまとめて話す。
「最近、ハラスメント対策がうるさくなってきたでしょう。労働局の指導も厳しく、当社としても法令に沿った規程類を整備せざるを得なくなりまして。あとは社内研修用のマニュアルなんかも必要ですね」
近藤の態度はどこか慇懃で、ただ必要最低限の言葉にとどまる。小山は資料を受け取りながら、ちらりと目をやると、書面にはやけに“就業環境の保持”に関する条項の修正案が赤字で書き込まれている。その赤字の筆圧が異様に強い。まるで書いた人物の焦燥や苛立ちがにじみ出ているようだった。
「ちなみに、御社ではハラスメントに関する具体的なトラブルが現時点で起きているのでしょうか」
小山が尋ねると、近藤は少し言葉を飲み込むようにしてから答えた。
「いえ……ええ、まあ。多少、セクハラに関する苦情や、パワハラだと言う社員の声が出たりはしているようですが、まだ正式な訴えには至っていません。ただ、念には念を入れて、早めに整備しようというのが経営陣の方針です」
そう言う目の奥にどこか陰が差す。言えないことがあるのか、それとも単なる事務的な業務か。小山は表情を変えずに頷いた。企業からのこうした依頼は珍しくない。しかし、一度企業の奥深くに足を踏み入れれば、そこにはえげつない人間模様が広がっていることがある。今回も、ただの形式的な規程整備にとどまるのか。それとも……。
第四章 社内の暗部
前原の件と東邦産業の件、それぞれ別個の仕事として進めていた小山だったが、奇妙な共通点に気づくのはもう少し後のことだった。前原から持ち込まれるパワハラの証拠書類と、東邦産業で進める就業規則の改訂作業。全く無関係に思えた二つの事象が、ある断片的な情報を通じて線で結びついていくのである。
前原のパワハラ上司は本社の部長職で、大手企業から出向してきている人物だという。聞くところによれば、彼が会社の取引先を拡大させるために奔走している最中、些細なミスをした部下を集中的に責め立てる癖があるらしい。前原の同僚がひそかに口にしたという。「あの上司の背後には、古巣のもっと大きな組織があるんじゃないか」と。
一方の東邦産業は業界内のネットワークが広く、さまざまな企業と連携している。中には前原の会社とも取引関係にあるかもしれない。小山は企業同士の繋がりにうといわけではないが、今回の案件を通じて偶然にも「あの会社と取引がある」という情報を耳にした。それはどこか薄ら寒い予感を帯びていた。
そしてある夜、小山が仕事を終えて事務所を閉めようとした瞬間、階段下に一人の男が立っているのに気づいた。街灯の逆光で顔ははっきり見えないが、懐に手を入れている姿が妙に不気味だった。小山が「どちら様ですか」と声をかけると、男は何も答えずに踵を返し、人混みのほうへ紛れ込んでいった。かすかに聞こえた靴音だけが、夜の路地に残っている。あるいは前原の上司サイドの人間か、あるいは東邦産業に関わる何者か。小山の胸に、疑念が深く刻まれた。
第五章 会社の“隠蔽工作”
前原がついに内容証明郵便を送付した翌週、彼女から連絡が入った。声は震え、ひどく混乱している。
「小山先生……会社側が動き出して、社内で私のことを『虚言癖がある』と噂しているんです。上司が『あいつは精神的に不安定だ』って言いふらして……。もうどうしたらいいか」
書類を送った結果、会社側が“言いがかり”と印象操作を始めるのはよくあることだ。だが、そこに法的根拠がなくとも、社内の空気が「前原が会社に害をなそうとしている」という方向に傾く恐れがある。孤立を深めてしまうかもしれない。小山は慎重に言葉を選んだ。
「今の段階では、会社の言う“虚言”に対して反証するためにも、これまで上司から受けたメールやメモなどの証拠をしっかり管理してください。もし、いよいよ労働審判や裁判など法的手続きに進む場合は、僕と提携している弁護士がいます。必要ならすぐにご紹介します」
前原はまだ訴訟に踏み切る覚悟がないようだったが、社内での状況悪化に怯えている。小山はなんとか励ましつつも、「会社の不当な言い分に反論する陳述書」の文面作成を手伝うことを約束した。会社側が社内調査を行うなら、その過程で前原の正当性を裏付ける証拠を提出する余地もある。
その夜、小山は静まり返った事務所のデスクランプの下、前原の陳述書の下書きを作成していた。パワハラの具体的日時、場所、上司の発言、証人となり得る同僚の名前——行数を埋めるたびに、想像を絶する苦悩が彼女を襲ってきたのだろうと感じる。小山はふと、これが単なる業務以上の重みを持ち始めていると自覚した。彼女を一人にしないためにも、行政書士という立場の限界を理解しつつ、可能なサポートを続けねば——。
第六章 東邦産業の“研修会”
一方で、東邦産業ではハラスメント防止の研修会が開かれることになり、小山は資料の作成支援を求められた。近藤係長と経営陣が主導する形で、全社員に対して「パワハラ・セクハラの定義や具体例」「社内相談窓口の利用方法」などを周知する狙いがある。小山はパワハラ・セクハラの法的な定義や判例を踏まえながら、研修に使用するレジュメやスライドの案をまとめていた。
しかし、小山が提出したドラフトを見た近藤係長は、妙に渋い顔をする。
「うーん、もう少し当たり障りなくお願いできませんか。具体例も、あまり突っ込んだ記述は不要というか……。あくまでも形式的に終わらせたいんですよ、うちとしては」
小山は意外な思いで近藤の表情を観察した。通常、企業がこうした研修を行う場合は、自社への信頼を高める意味でも「かなり真剣に取り組んでいます」とアピールしたがるのだが、近藤の態度はそれとは逆だ。「あまり突っ込んだ説明はしないでほしい」ということは、裏を返せば「社内で大きく騒がれると困る」事情があるのかもしれない。
「わかりました。企業様のご要望には可能な限り沿いたいと思います。ただ、実効性のあるハラスメント防止策をアピールするなら、具体事例を示したほうが——」
「いや、形式だけでいいんです。とにかく“法令を満たしてます”という証明が欲しいだけですから」
近藤の言葉には冷たさすら感じられた。これでは“ハラスメントを根本的に解決したい”というより、“表向きだけ整えておけばいい”と言わんばかりだ。小山は複雑な気持ちを抱えたまま、近藤が提示したレベルに合わせた資料を作り直す。それでも、最低限必要な事項は抜かないように気を配りながら——。
第七章 交錯する企業と個人
研修会当日、小山はオブザーバーとして社内の説明を見守るために東邦産業を訪れた。広い会議室には数十名の社員が集められ、前方のスクリーンには「ハラスメント防止研修」と書かれたスライドが映し出されている。壇上で話すのは近藤と、もう一人の人事部長らしき人物。だが、小山の目は後方の席にちらりと座った女性に釘付けになった。
どこかで見覚えのある姿——そう、前原可奈子に似ている。まさかと思い、もう一度確認するが、別人のようだ。しかし顔の輪郭や醸し出す雰囲気が妙に似通っている。その女性は淡々とメモを取っていて、周囲に溶け込んでいる。小山は意識的に視線を切り替え、壇上の近藤に集中しようとした。
しかし、そこで耳に飛び込んできたのは予想に反する言葉だった。
「当社はこれまで、セクハラ・パワハラを含む社内ハラスメントを非常に重く受け止めてまいりました。今後も社員一人ひとりが安心して働ける環境を築くために、研修を通じて意識を高めていただきたいと考えております」
その言葉とは裏腹に、近藤の目はどこか憂鬱そうだ。社員たちもどことなく気のない表情でスライドを見ている。こうした企業はどこにでもある——そう思っていた小山だったが、しかしこの空気感は異常だった。まるで“やりたくないことを無理矢理やっている”ような、あるいは“外面を整えるためのセレモニー”を淡々と遂行しているだけのように見えた。
研修が終わると、近藤がこそこそと小山に近づき、早口で言う。
「今日はご苦労様でした。資料のおかげで無事終わりました。あとは就業規則の改訂を急いでほしいんです。早めに届け出を済ませたいので」
そう言い残して、近藤は一礼もそこそこに立ち去った。小山は何とも言えない虚脱感を覚える。問題の根本にメスを入れる気がない企業——そんな印象が拭えなかった。
第八章 追い詰められた声
研修会から一週間ほど経ったころ、前原から再び助けを求める電話が入った。声は涙混じりだ。先日の内容証明郵便に対し、会社が「問題はすべて解決済み」「彼女の主張には根拠がない」と回答してきたのだという。
「社内の誰も私の味方になってくれません。小山先生、もう……訴訟しか道はないんでしょうか」
苛立ちと絶望がにじむ声に、小山の胸は痛む。訴訟に踏み切れば、時間も費用もかかる。会社の対応によっては長期戦になるだろう。小山の立場でできるのは、示談書や証拠整理、さらに必要に応じて弁護士の紹介にとどまる。だが、最終的にどういう行動を取るかを決めるのは前原自身だ。
「焦らずに考えてください。まずは労働局のあっせんや、労働基準監督署への申告という手段もあります。会社が本気で取り合わないなら、いよいよ裁判の可能性も視野に入りますが、その場合は弁護士の先生との連携が必要です」
前原は少し落ち着きを取り戻したようだったが、やはり迷いが強い。自分がそこまで大事にして本当に良いのか。仕事を失うリスクや精神的負担を考えると尻込みしてしまう。その葛藤は、まるで見えない茨の道を歩くように、小山にも痛々しく伝わってきた。
第九章 企業間の影
そんな折、小山は偶然ある情報を手に入れる。知り合いの経営コンサルタントが、軽い雑談の中でこう言ったのだ。
「最近、東邦産業の名前を頻繁に耳にするんですよ。あそこと取引のある会社が、社員のハラスメント問題で内部告発されそうになっているとか……。どこか別の企業から来た上司が、相当強権的らしいんですよね」
小山はハッとした。別の企業から来た強権的上司……それはまさに前原が苦しめられている上司の特徴と重なる。つまり、東邦産業と前原の会社との間には想像以上に太いパイプがあるのかもしれない。
もし、東邦産業が自社の評判を落とさないよう、関連企業のハラスメント問題をもみ消す方向に動いているとしたら——。小山は全身に鳥肌が立つ思いだった。それは単なる臆測かもしれない。しかし、ハラスメントが起こる陰には常に組織の利害が絡む。その利害に翻弄される人々を、小山は見てきた。
第十章 悪意の渦
前原への嫌がらせは次第にエスカレートしていた。彼女の机に陰湿なメモが置かれる、職場であからさまに無視される、仕事を取り上げられ「席に座っているだけ」で過ごす日々が増える——。小山に相談できるだけまだ救いがあるが、精神的なダメージは大きい。
一方の東邦産業では、あれほど急かしていた就業規則の改訂が完了し、会社としては書類を労働基準監督署に届け出る段階に至っていた。近藤からの連絡で、小山は最終チェックを進めるが、その内容はあくまでも「表面的にハラスメント防止を謳う」だけで、具体的な救済手段や罰則規定は曖昧に記載されている。まるで「これで義務は果たしただろう」と言わんばかりの姿勢だ。
そのとき、小山のスマホが震えた。番号非通知の着信。出ると、あの低い男の声が再び聞こえる。
「余計なことはやめろ。あんたが関わっても何も変わらない」
小山は鼓動が早まるのを感じた。喉の奥が渇く。電話の先で男は続ける。
「会社のことに首を突っ込むな。わかったな」
冷たい言葉とともに、一方的に電話が切れた。前原の会社と東邦産業、二つの企業が裏で繋がっているのか。それともまったく別の勢力が小山を牽制しているのか。頭の中で疑念が渦巻く中、小山は意を決した。ここで尻込みしては、前原のような弱い立場の人間はどこにも助けを求める先がなくなってしまう。
第十一章 あくまで行政書士として
小山はすぐに前原へ連絡を取り、「もし会社が更なる嫌がらせを続けるなら、労働審判制度の活用も視野に入れましょう。あなたが望むなら、弁護士を交えて交渉することもできる」と伝えた。前原は少しばかり覚悟を固めつつあるようで、小さく息を吐き、「わかりました、お願いします」と震える声で応えた。
同時に、小山は東邦産業との今後のやり取りを、できるだけ記録に残そうと考えた。形式的なハラスメント対策を進める企業の姿勢を、結果的には助長することになってはいないか——自問自答の末、行政書士としての職責と限界を再確認する。「文書作成と手続きの代理」の範囲を守りつつ、しかしこの闇を見て見ぬふりはできない。
第十二章 暗躍する影
そんなある日、小山の事務所に思わぬ来客があった。若い男性で、名刺には「株式会社アイシス 営業部」とある。聞けば、東邦産業の下請けとして何年も取引を続けている会社だという。男性は所在なげに視線を泳がせながら言った。
「……実はうちの社員が、『東邦産業さんからセクハラを受けている』と訴えてきまして。社としても大事にしたくないので、穏便に示談で済ませたいんです。そこで、行政書士の方に示談書を作成してもらえたらと……」
急な依頼だったが、小山は驚きとともに妙な確信を深める。やはり東邦産業は“体裁”を重んじる企業でありながら、内部には多様なハラスメントが存在しているのではないか。しかも、自社ではなく下請け企業の社員に“加害”が及んでいる可能性もある。だが男性の様子を見るに、東邦産業が何か手をまわして「大ごとにするな」と圧力をかけたのかもしれない。
「わかりました。示談書の作成ですね。ただ、詳細をうかがわないと文書に具体的な内容を盛り込めませんので……。その社員さんと直接やり取りができればと思うのですが」
小山が言うと、男性はまるで何かから逃げるように視線を下げる。「いえ、それは無理です。本人はもう会社を辞めようとしているので……。私が代理で話をしますから」。かくしてまた一つ、東邦産業にまつわるハラスメント疑惑が浮上することになった。
第十三章 暴かれる繋がり
日が経つにつれ、小山のもとには複数のハラスメント事例が集まってきた。前原の件、下請け社員のセクハラの件、そして東邦産業の就業規則の改訂。まるで綿密に張り巡らされた蜘蛛の巣のように、糸が交錯していく。そこには明らかに東邦産業とその関連会社が絡んでいる事実を示す断片的な証拠が並んでいた。
小山は一人の行政書士に過ぎない。訴訟代理人として企業と戦うことはできないし、警察権力のように強制捜査をする権限もない。しかし、法的手段を講じるための土台を作ることはできる。その思いが彼を奮い立たせていた。
「これはもう、個々の社員の問題では済まされない。組織ぐるみでハラスメントを隠蔽しようとしている恐れがあるのでは?」
ある深夜、オフィスの蛍光灯だけがまばゆい光を放つ中、小山は前原や他の相談者たちの証拠をまとめ、必要な場合に備えて弁護士への連携資料を作成し始めた。もしこの先、複数の被害者が声を上げるなら、集団的な動きに発展する可能性もある。一方で、小山への脅迫と思しき電話や無言の影も増えるだろう。それでも後戻りはできなかった。
第十四章 決断のとき
やがて、前原から「会社を提訴することを決心した」との連絡が入る。会社の言う「解決済み」は虚偽であり、彼女の尊厳を踏みにじる行為が絶えないこと。これ以上、社内での改善は望めないと判断したのだという。小山は弁護士を紹介し、これまで作成してきた文書や証拠資料をすべて渡した。
「小山先生、本当にお世話になりました。いろいろ大変だと思いますが、私……もう逃げたくないんです」
彼女の声に迷いはなかった。小山は「あなた自身が決めた道なら、きっと先が見えてきます」と伝え、応援の言葉を添えた。行政書士としての役割はひとまず果たした格好だが、現実はこれからが正念場だろう。会社の手段を選ばぬ反撃が予想されるからだ。
第十五章 結末への序曲
一方の東邦産業では、先のセクハラ示談書の作成依頼もなんとか完了し、形式的には「もうトラブルは収束した」と社内外に向けて発表していた。改訂後の就業規則も「社内チェックをクリアした」と近藤から連絡を受け、小山は戸惑いながらも提出書類を整えている。
だが、その裏では下請け社員の退職が相次ぎ、「東邦産業はセクハラ、パワハラの温床だ」という噂がインターネット上で囁かれ始めていた。近藤や会社幹部は「デマだ」と一蹴しているようだが、内情を察する小山にとっては穏やかならざる事態である。
ある夜、小山は再びあの番号非通知の電話を取った。相手はいつもの男ではなく、どこか甲高い声の人物だった。
「これ以上の口出しはやめていただけませんか? 当社は適切に対応しています。あなたの書類作成が、かえって余計な混乱を招いているんですよ」
薄笑いの混じるような口調に、小山は身震いを覚えた。しかし、彼は動じずに言う。
「僕はあくまで依頼を受けて文書を作成しているだけです。もし問題の根本が解決されるなら、それに越したことはない。あなた方が本当に社員の立場を考えているなら、こんな牽制をしなくても済むはずですよ」
相手は一瞬口籠もり、それから「後悔しないように」とだけ残して電話を切った。静けさだけが事務所を包み込む。松本清張の描く社会の闇に似ている——小山は、そんな感慨を抱きながら深い息をついた。
第十六章 闇を抉るペン
前原の決断からしばらくして、彼女が弁護士を通じて会社を正式に訴えたとの知らせが入る。それに呼応するかのように、東邦産業の関連会社で働く別の女性社員も「パワハラ上司に悩まされている」と表明し、告発文を書き始めたという情報が飛び込んできた。
小山の元には次々と相談が舞い込み、事務所はかつてない忙しさを見せる。行政書士としてできることは限られているが、それでも示談書や告発文の作成、労働局や労基署へ提出する書類の整備など、裏方の仕事は山積みだ。小山は疲労にまみれながらも、ペンを握る手を止めない。これは誰かにとっての希望の糸かもしれないのだ。
第十七章 浮かび上がる真実
前原の訴訟が始まると、会社は当初「パワハラの事実は一切ない」と主張していた。しかし、彼女が上司の暴言を録音していた音声データや、内容証明郵便を郵送した後に実施された“社内調査”の杜撰さが公になるにつれ、会社側は徐々に追い詰められていった。表面を糊塗した文書では誤魔化せない真実が、法廷の場で少しずつ明かされていく。
小山はあくまで傍観者として、弁護士から送られてくる情報を受け取りながら、心の中で前原を励ます日々を送っていた。道は険しい。会社の圧力に屈して途中で和解に応じてしまう例も多い。しかし前原は一歩も引かずに戦っているという。
一方、東邦産業では内部からの声が高まりつつあった。形式的に改訂した就業規則が、結局は絵に描いた餅に過ぎないという批判が社内外で囁かれ、それがSNSや転職サイトの口コミなどに広がっている。それでも会社側は「当社は適切に対応している」と宣伝を続け、問題をうやむやにしようとしていた。しかし——そんな表の動きとは裏腹に、一部の社員が小山の元を訪れ、「本当は会社に裏切られた思いです」と告白するケースが増えてきた。
第十八章 暗闇の先の光
前原の訴訟は、一年あまりに及ぶ長い戦いの末、会社側に一定の賠償責任と謝罪文の提示を求める和解案で決着を迎えた。上司の行為がパワハラとして違法性を帯びると認定されたことは、前原にとって大きな救いとなった。会社側が罪を認めたわけではないが、それでも「事実上の勝利」であると言える。
訴訟が終わった翌日、前原は小山の事務所を訪れ、深々と頭を下げた。
「ここまで来られたのは、小山先生が私の話を聞いて、書類を作ってくれたからです。ありがとうございます」
小山は「僕は大したことはできませんでしたよ」と控えめに笑う。だが、その笑みの裏には、前原が勝ち得た一歩が、同じ苦しみにあえぐ人々に勇気を与えるだろうという確信があった。
一方、東邦産業は数多くのハラスメント疑惑を抱えたまま、社内改革を進めるのか、それとも引き続き隠蔽を図るのか。小山が見た限りでは、後者である可能性が高かった。だが、いつかは「企業の人間関係」にメスが入る時が来る。そのとき、彼らがどんな態度を取るのか——。
終章
数カ月後の初夏。雨上がりの空から射す柔らかな日差しを受け、小山は事務所の窓を開け放っていた。扇風機が古い書類の匂いをかき混ぜる。あの騒動から前原は別の会社で働き始め、下請け企業でセクハラを受けた社員たちも弁護士を介して和解手続きを進めていると聞く。いずれも決して楽な道ではなかったが、少なくとも“声を上げる”という選択をしたのだ。
無論、企業や組織内のハラスメントがすべて解消されたわけではない。多くの人が沈黙を余儀なくされ、苦しんだ末に退職していく現実は今もある。だが、小山は確かな思いを胸に抱いていた。「行政書士として、文書作成や手続き支援を行うことで、わずかながらでも人々の苦しみを軽減する一助になれる」。
ふと机を見下ろすと、目立たないところに置かれた電話メモに気づく。最近、番号非通知の着信はパタリと止んだ。あの暗い声や圧力が消えたわけではないだろう。だが、それは社会の暗部として、これからも形を変えて生き続けていく。
小山はデスクに腰掛け、今日も新たに届いた相談案件に目を通し始める。パワハラ、セクハラ、マタハラ——あらゆるハラスメントがまだまだ渦巻いている。それでも、彼は一つひとつの事案に向き合い、相談者と共に“書く”ことで道を切り拓こうとする。松本清張の筆が社会の闇を抉ったように、小山のペンもまた、企業の闇を白日の下にさらす手段となるかもしれない。
人間の心の奥底に潜む欲と利害。それが複雑に絡み合い、組織を動かす歯車を狂わせる限り、ハラスメントはなくならないかもしれない。けれど、諦めなければ救いはある——そう信じながら、小山は今日も地道に文書を作り、電話を取り、相談者の不安な声に耳を傾ける。扇風機の風が一枚の書類を捲り上げ、そこに書かれた「パワハラ」と大きく赤字で書かれた見出しが、初夏の光にちらついていた。


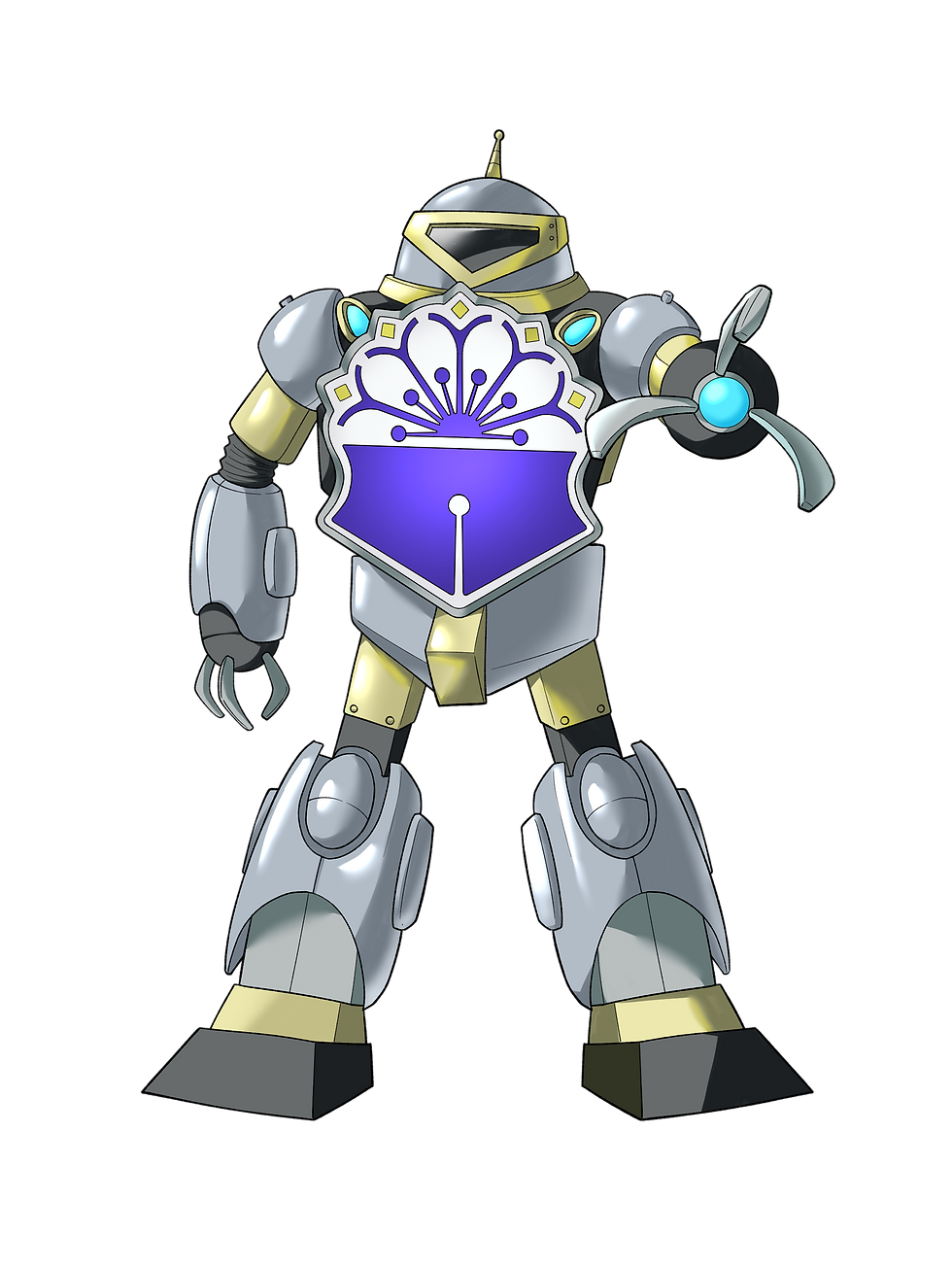


コメント